電気基本料金とは?分かりやすく解説!節約術も紹介
コラム
2025.10.24
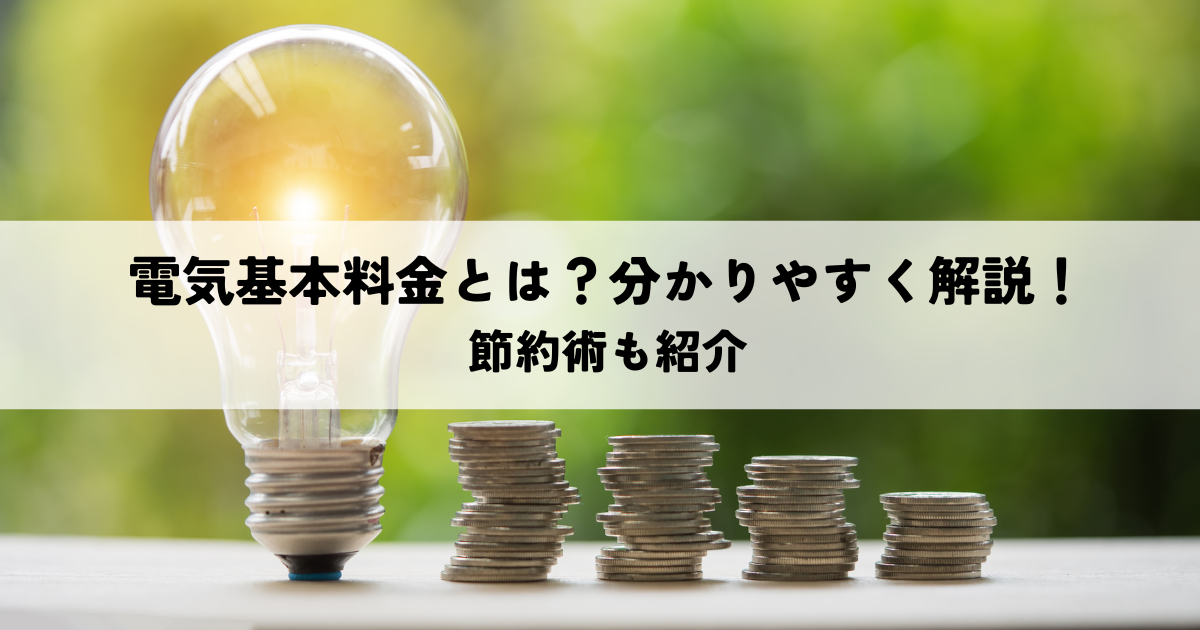
電気料金の請求書を見て、基本料金の項目に疑問を感じたことはありませんか?
毎月の電気代、実は使用量だけでなく、基本料金も大きく影響しているのです。
この基本料金を理解することで、電気料金全体を節約できる可能性が見えてきます。
今回は、電気の基本料金について、その仕組みから節約方法まで、分かりやすくご紹介します。
電気の基本料金とは何か
基本料金の定義
電気の基本料金とは、毎月の電気使用量に関わらず、必ず発生する料金のことです。
発電設備の維持管理費、送電網の保守費用、電力会社従業員の給与、事務処理費用など、電力供給のための様々なコストを賄うための費用と考えてください。
これらのコストは、電気をどれだけ使っても使わなくても、電力会社は負担し続けなければなりません。
電力会社によっては「最低料金」と表記される場合もありますが、内容は同じです。
例えば、東京電力パワーグリッドなどの送電会社への託送料金も、基本料金に含まれる重要な要素です。
基本料金の仕組み
基本料金の仕組みは、電力会社によって「アンペア制」と「最低料金制」の2種類があります。
アンペア制は、契約アンペア数に応じて基本料金が決まります。
契約アンペア数が多いほど、一度に使える電力量が多くなるため、電力会社はより大きな設備投資と維持管理が必要となり、基本料金が高くなります。
例えば、20A契約と40A契約では、後者の方が基本料金が高くなります。
一方、最低料金制は、契約アンペア数に関わらず、一定の最低料金が設定され、それ以下の使用量であってもこの料金が請求されます。
これは、電力供給インフラを維持するための最低限必要な費用を確保するためです。
使用量が最低料金相当を超えた分については、使用量に応じて料金が加算されます。
これは、使用電力量に応じて発電や送電にかかるコストが増加するためです。
基本料金の計算方法
アンペア制の場合、基本料金は契約アンペア数と電力会社の料金プランによって決定されます。
電力会社の料金表には、契約アンペア数ごとの基本料金が明確に記載されているので、確認することで具体的な金額を把握できます。
例えば、東京電力エナジーパートナーの料金プラン「従量電灯B」では、20A契約の基本料金と30A契約の基本料金が明確に示されています。
最低料金制の場合、基本料金は一定額で、例えば月額1000円など、事前に決められています。
使用電力量が一定量(例えば50kWh)を超えた場合に、超過分に応じて電力量料金が加算される仕組みです。
これは、使用電力量に応じた発電コストを反映するためです。

電気の基本料金の決定要因
契約アンペア数
契約アンペア数は、一度に使える電力の最大量を示し、基本料金に大きく影響します。
契約アンペア数が大きいほど、基本料金が高くなります。
これは、より大きな電力を供給するための設備投資が必要となるためです。
ご家庭の電化製品の消費電力と同時使用状況を考慮し、適切なアンペア数を契約することが重要です。
例えば、エアコン、電子レンジ、電気炊飯器などを同時に使用する場合、消費電力が大きくなるため、契約アンペア数を高めに設定する必要があります。
しかし、必要以上に高いアンペア数を契約すると、基本料金が無駄に高くなってしまうので注意が必要です。
電力会社の料金プラン
同じ契約アンペア数でも、電力会社や料金プランによって基本料金は異なります。
これは、各電力会社の経営戦略やコスト構造、そして、利用する発電方法(火力発電、原子力発電、再生可能エネルギーなど)の違いが影響しているからです。
複数の電力会社を比較し、ご自身の使用状況(年間の使用電力量、使用時間帯など)に最適なプランを選ぶことで、基本料金を節約できる可能性があります。
例えば、夜間の電力使用が多い家庭であれば、時間帯別料金プランが有利になる可能性があります。
その他影響要素
基本料金は、契約アンペア数と料金プランが主な決定要因ですが、電力会社の設備投資状況や燃料価格の変動、送電網の維持管理費用、そして、政府の政策(再生可能エネルギー促進政策など)なども影響する可能性があります。
例えば、原油価格の高騰は火力発電のコスト増加につながり、基本料金に影響を与える可能性があります。

電気料金の基本料金を安くする方法
契約アンペアの見直し
契約アンペア数が大きすぎると、基本料金が高くなってしまいます。
ご家庭で同時に使用する電化製品の消費電力を確認し、必要最小限のアンペア数に契約を見直すことで、基本料金を削減できます。
例えば、消費電力の合計が5kW程度であれば、20A契約で十分な場合があります。
ただし、アンペア数を小さくしすぎると、ブレーカーが落ちやすくなり、生活に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。
専門業者に相談して最適なアンペア数を判断することも有効です。
節電対策の重要性
基本料金は使用量に関係なく発生しますが、電力量料金は使用量に比例して増加します。
そのため、節電対策は電気料金全体を削減する上で非常に重要です。
LED電球への交換、こまめな電源オフ、省エネ家電の使用、待機電力の削減、エアコンの設定温度を1℃上げる(冬は下げる)だけでも、電気代の節約に繋がります。
冷蔵庫の詰めすぎは冷蔵効率を下げるため、注意しましょう。
さらに、太陽光発電システムの導入も検討することで、発電コストを削減し、基本料金の負担感を軽減できます。
まとめ
電気の基本料金は、使用量に関わらず毎月発生する料金で、発電設備の維持費、送電網の保守費用、人件費などを賄うためのものです。
基本料金の仕組みはアンペア制と最低料金制の2種類があり、契約アンペア数や電力会社の料金プランによって金額が異なります。
基本料金を安くするには、契約アンペア数の見直し、電力会社の比較検討、そして節電対策が効果的です。
これらの方法を組み合わせることで、毎月の電気料金を節約し、家計への負担を軽減することができます。
賢く電気料金と向き合い、節約生活を目指しましょう。
電力会社への問い合わせや、専門家への相談も有効な手段です。



